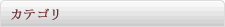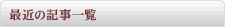■ 研究員ブログ34 ■ 『アルカサル -王城-』と武士の鎌倉

先日の関東地方は、すごい雪でしたね。
窓の外を雪が降りしきる眺めは、
学生時代を思い出して懐かしくなるものでした。
休みなのをいいことに、一歩も外には出なかったのですが……。
それで何をしていたのかというと、
世界遺産アカデミーのKさんから貸してもらったマンガ、
『アルカサル-王城-』を読んでいました。
これがなかなか面白いのです。
実在したカスティーリャ国王ペドロ1世を主人公とする物語で、
読んでいると、14世紀頃の国王と貴族、騎士などの関係がよく解ります。
塩野七生さんの『チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷』が好きな人は、
このマンガも面白く読めるのではないでしょうか。
カスティーリャ王国のペドロ1世は、
王権を強化するために貴族階級やローマ教皇と対立し、
その半面で、ユダヤ人を重用したりイスラムの文化を取り入れるなど、
カトリック以外の価値観を積極的に持ち込みました。
彼が築いたとされるセビーリャのアルカサル(宮殿)が、
イスラム様式を取り入れた、とても美しいムデハル様式になっているのも、
当時のイベリア半島にカトリックとイスラムの文化が混在していた、というだけではなく、
ペドロ1世のこうした嗜好や政治スタイルも影響しているのだと思います。
このアルカサルは『セビーリャの大聖堂、アルカサル、インディアス古文書館』として
世界遺産登録されています。
また『アルカサル-王城-』を読んでいると
貴族や騎士たちが、いとも簡単に国王を裏切ることに驚かされます。
貴族が利害関係から国王を裏切るのはまだ解りますが、
騎士たちもが国王に背くのは、騎士と国王との関係性に理由があります。
キリスト教の世界で騎士というのは、
国王ではなく「神」に誓いをたてた戦士です。
なので最も忠義を尽くさなくてはならない相手は「神」なのです。
では国王と騎士の関係はどうなっているかといえば、
国王と騎士は、報酬(領地など)と軍役による契約関係で、
国王が報酬を与える代わりに、王国に何かあった場合には騎士が参戦する。
その参戦も日数が決まっていたりします。
そうした契約関係なので、
例えば国王が「神」に背く行いや命令をした場合には、
「神」に従って国王との契約を破棄することが出来ます。
中世の騎士たちが国王を裏切る一番の理由は、
貴族たちと同じく自己の利益のためですが、
その際の大義名分になるのが「神との誓い」でした。
騎士道物語のイメージが日本でも広がっているため、
騎士というのは清廉潔白、国王や女性に忠義を尽くす存在の気がしますが、
実際は、自己の利害のために国王や主人を裏切るという騎士が少なからずいました。
中世のヨーロッパというのは、本当に混沌とした時代だったのです。
「神」に誓いを立てる騎士の姿は、
主人と直接主従関係を結ぶ日本の武士とは大きく異なっています。
この武士を前面に出して世界に日本文化をアピールしているのが
現在推薦書を作成中の「武家の古都・鎌倉」です。
「武家の古都・鎌倉」では、
武士をヨーロッパの騎士やイスラムのマムルークと比較しており、
比較対象として『バレッタの市街』や『ロドス島の中世都市』、
『クラック・デ・シュヴァリエとカラット・サラーフ・アッディーン』など
32の世界遺産や暫定リスト記載遺産が挙げられています。
世界に対してアピールしやすい「サムライ」を前面に出して、
その武士(サムライ)が初の武家政権をひらいた都市、鎌倉として
世界遺産登録を目指すのは、日本人としては理解しやすいものです。
ただ世界遺産として世界(他国)から見たときに、
一目でわかる解りやすい価値、というのが足りない気もします。
理由を説明してもらって「なるほど!」となるのではなく、
何も知らなくても「これぞニホンのサムライワールド(?)!」となるような
見た目のすごさ、というか。
セビーリャのアルカサルなどが持っている魅力はまさに、それです。
僕も鎌倉は大好きでよく行きますし、
鶴岡八幡宮や建長寺など個別の資産が素晴らしいことは知っています。
ただ、三方を山に囲まれ、一方を海に開いた場所に、
禅宗の寺社や交通路、港などを効果的に配置している、ということの
「サムライ」とのつながりや魅力が、すこし伝わりにくい気がするのです。
鎌倉が世界遺産に登録されることを心より願っています。
そのためには、「武家の古都・鎌倉」の魅力を存分に世界遺産委員会に伝える
推薦書の作成と日本政府代表団のPR力に期待したいと思います。
『アルカサル-王城-』を読みながら、
そんなコトを考えた2013年の始まりでした。