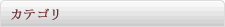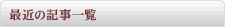2013年度 世界遺産アカデミー特別講座(前編)前ユネスコ事務局長顧問・服部英二氏『ボロブドゥールの語るもの ~建築様式に見る天山思想とは?~』
前ユネスコ事務局長顧問・服部英二氏による第3回特別講演会
『ボロブドゥールの語るもの ~建築様式に見る天山思想とは?~』が、
2013年5月6日(月・振替休日)に開催され、大好評のうちに終了いたしました。
このたび、服部氏のご厚意によって、特別講演会の全容を
前・後編の2回に分けて、公開させていただくことになりました。
『ボロブドゥールの語るもの ~建築様式に見る天山思想とは?~』(前編)
前ユネスコ事務局長顧問 服部 英二
皇居の緑がきれいに見えて、この会場は素晴らしい環境ですね。実は、このパレスサイドビルとは縁が深く、パリのユネスコ本部で世界遺産の仕事をしていた頃、よく訪れました。というのも、当時まだ、日本は世界遺産条約を締結していませんでしたが、パリから帰国し、政府関係者に世界遺産条約締結を働きかけていた時、前向きに論陣を張ってくれた最も強力なマスコミが、毎日新聞社だったのです。そういった関係で、パレスサイドビルには、よく足を運んだものでした。今回で、世界遺産アカデミーでの講演は3回目となりますが、この場所で講演会を開催できることは、非常に懐かしく、昔の思い出がよみがえるようです。
■文明間の対話
さて、今日は、ボロブドゥールをシンボルとして取り上げて、「文明間の対話」について、お話を進めていきたいと思います。「文明間の対話」という言葉は、私が1985年に「シルクロード総合調査計画」を起草した時、その趣意書の冒頭に「シルクロードとは、海の道、陸の道を問わず勝れて文明間の対話の道であった」と記したのが、初出です。この言葉はたいへん多くの国々を惹きつけたようです。シルクロード総合調査隊には、30カ国、2,000名を超える有識者たちが集まりました。取り上げたメディアは数知れず、調査隊に同行したテレビ局だけでも6社を数えました。草原の道、砂漠の道、海の道に及んだシルクロードの総合調査は、最終的に6年間もかけた国際的プロジェクトになりました。
服部英二氏著書 『文明は虹の大河』 、 『文明間の対話』
このように多くの人々を惹きつけたキーワードが、「文明間の対話=Dialogue of Civilizations」でした。ただ、この言葉が定着するのには、10~15年の歳月がかかりました。今でこそ「文明間の対話」という言葉は、皆さんにも聞き慣れた言葉になっているかと思います。私の著作、『文明間の対話』は、当初、講談社の現代新書から「文明の交差路で考える」というタイトルで1995年に出版したものですが、その打ち合わせの時、私が書籍名を「文明間の対話」と提案したところ、講談社の担当者は、「“文明間の対話”という言葉は耳慣れない言葉ですね」と難色を示したのです。そこで講談社が考えたタイトルが「文明の交差路で考える」でした。私は「文明間の対話」を使いたかったのですが、当時この言葉は一般的ではありませんでした。しかし、おかげ様で現代新書の本も好評を博し、売り切れとなりました。そこで、幾つかの章を加え、元の文章にも手直しを施した改訂版を、麗澤大学出版会から出すことになって、ようやく、当初のタイトル「文明間の対話」を付けて出版するにいたったわけです。
その後、この言葉を、サミュエル・ハンチントン著『文明の衝突』にぶつける人が現れます。それが、当時、イラン・イスラム共和国の大統領だった、モハンマド・ハタミ氏でした。ハタミ大統領は、1998年の国連総会で「2001年を文明間の対話の国際年にしよう」と提案しました。この2年前の1996年に、サミュエル・ハンチントンが『文明の衝突』を出版していました。「東西冷戦の終結後、国際社会では、文明の狭間で争いが起こる」としたこの論文で、ハンチントンは、文明を宗教と結びつけ、宗教間の争いを予測したのです。多くのマスコミがこの論文を取り上げ、各国でその翻訳本が出版されると、世論の動きは、徐々に、「文明の衝突」という概念を受け入れ、まるで「文明の衝突」が必至であるかのような流れになってしまいました。このハンチントンの考えに対して、ハタミ大統領が国連に提示した言葉が、シルクロード・プロジェクトのキーワードとなった「文明間の対話」でした。ハタミ大統領の提案を聞いた各国の代表たちは、「たいへん素晴らしい提案だが、イランからの提案というのは如何なものか」など、総論賛成の一方で疑問符もつく、といった反応を示しました。が、最終的には、満場一致でこの提案が採択され、2001年は「文明間の対話国際年」となりました。ハタミ大統領の意図は、ユネスコ・プロジェクトの「文明間の対話」という言葉を、「文明の衝突」という負の概念に対峙させ、国際的に定着させないよう、阻止するところにありました。数年後、パリでハタミさんにお会いした際、「私はユネスコのシルクロード総合調査計画の立案者です」と自己紹介したところ、ハタミさんはたいへん喜ばれて、私に抱きついてくれたことを、今でも覚えています。
今日は、文明は絶えず対話する、そして文明は出会う、出会って新しい生命を宿し成長していく、という過程をボロブドゥールという、東アジアのひとつの世界遺産を取り上げながら、お話していきたいと思います。
朝焼けのボロブドゥール
こちらの写真は、まだボロブドゥールの復興工事が行われている頃のもので、午前5時ごろ、ボロブドゥールの東側に位置する母なる火山、メラピ山の頂上から太陽が顔を出す瞬間を捉えたものです。メラピ山が噴煙をあげていますが、ジャワでは、この山が聖山として崇められています。つい先日、「富士山」が日本独特の山岳信仰の象徴としての価値を認められて、世界遺産への登録がほぼ決定しそうだ、というニュースが飛び込んできましたね(2013年5月現在)。私もたいへん嬉しく思っています。6月の世界遺産委員会で登録されることは、間違いないでしょう。この山岳信仰に関係する文化財が、富士山の周辺にはきちんとした形で遺されている、とICOMOSも高い評価を下しているようです。
山岳信仰は、日本独自のものかと言うと、そうではありません。山岳信仰は、あらゆる国、あらゆる場所で確認することができます。メラピ山、現地では“ムラピ”と発音しますが、東方のブロモという山も含めて、ジャワでは聖山となっています。火を噴く山=火山が、世界中の多くの国々で信仰の対象とされてきました。富士山も火山です。このような信仰形態とボロブドゥールが無関係でないことに、私は気づくのですが、詳しいことは、また後ほど、お話します。
■開かれた世紀
まず初めにお話しておきたいことは、この地球上には、8世紀をピークに開かれた世界が存在していた、ということです。21世紀の今こそが、国際化の時代、グローバリゼーションの時代であり、昔はそうではなかった、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際はそうではありません。むしろ、今より開かれた世界が存在していた時代がありました。その最たるものが、7~8世紀。特に、8世紀です。その証しが、世界規模で存在した文化センターとして花開く、数多くの国際都市の存在です。例を挙げれば、アンダルシアのコルドバ、モロッコのフェズ、コンスタンチノプール(今のイスタンブールですね)、イラクのバグダット、セイロン(スリランカ)北端の都市アヌラダプーラ。セイロンと言えば、キャンディーやコロンボという都市が有名ですが、これらの都市はもっと新しいもので、アヌラダプーラは、セイロン・シンハラ王朝最初の首都です。ちなみに、これらの都市は、ほとんどが世界遺産の都市となっていますね。そして、中央ジャワ。中央ジャワとしたのは、ボロブドゥールを中心とする文化ではあるものの、ボロブドゥール自体は都市とはいえないからです。ボロブドゥールはチャンディー(寺院)なのです。ボロブドゥールから数十km離れた場所に、プランバナンという都市があります。しかし、他の都市と並列して、“プランバナン”とは表現できません。私は“中央ジャワ”という表現で、この地の文化センターの存在を表す方が適切だと考えています。さらに唐時代の長安と、日本の奈良。こういった都市群が一斉に文化の花を咲かせていくのがほとんど同じ時代、つまり8世紀なのです。8世紀には“国境”というものが存在しなかった、と考えて良いのです。大和の国の威信を示した東大寺の大仏の開眼式は、752年に行われました。この式典には多数の国々も参加しています。新羅(現在の韓国)や唐だけでありません。ベトナム周辺からの参加者の記録もあります。そして、この大式典の式典長は、ボーディ・セーナというインド僧が務めています。現在、両国国技館の起工式の式典長を外国人が執り行う、といったことが考えられるでしょうか? 8世紀の時代は、日本を代表する大仏の開眼式の式典長を、外国人に委ねる寛容さが普通だったのです。
また、“international”という言葉を捉えた時、“international”内の“national”部分、“Nation”には通常、大きく分けて、“民族”と“国”の2つの意味がありますが、この場合は、Nationを “国”ではなく、“民族”と訳すべきです。“民族”と訳すことで、民族同士が交流するという意味の、“International”となります。国際的に民族同士の交流が盛んだった8世紀を過ぎると、やがて閉ざされた時代がおとずれます。ヨーロッパでの11世紀に始まる十字軍の存在。これが敵対原因を創り上げる大きな要因であった、と私はみています。さらに世界が閉ざされていくのは、16世紀の大航海時代。ヨーロッパの独占主義が台頭していきます。東インド会社は当初、公益を求めて運営されていましたが、そのうち国粋主義に傾倒していきます。18世紀に“Nation States”、つまり、民族国家という考え方が成立します。純粋な国家という捉え方ではなく、民族そのものが国となる、という考え方です。18世紀以降、“National”は独占的な意味を持ち始めます。8世紀に実現した民族間の文化交流=International はその意味を徐々に変化させていき、“Nation States”の概念によって、決定的に“international” は失墜していきます。20世紀が“戦争の世紀”と呼ばれる大きな要因が、18世紀の民族国家成立による“international” の喪失にあると、私は考えています。

ボロブドゥール
■イスラム国が修復した仏教寺院
ボロブドゥールの修復作業に、私も関わっていたのですが、そこで見えてきたものは、文化の融合でした。イスラム教は、7世紀の初め、610年に、ムハンマドが啓示を受けたことに始まります。あっと言う間に中東一帯を席捲し、8世紀にはインドや北アフリカ、イベリア半島すらもイスラム教の勢力下に入りました。ところが、インドより東方に広がっていくには、意外と時間がかかっています。8世紀に、アラビアのダウ船が、広東やインドネシアに到着はしているのですが、これは単なる交易であって、イスラム教の布教活動は行われていません。イスラム教が宗教として東南アジアに定着するのは、14世紀から15世紀の始めです。イスラムは東に進むほど、性格を変えていく。つまり、土地の文化と融合していきます。まさしく、文明間の対話です。イスラム教も、東の文化と出会い、変質して寛容になっていくのです。
これは聞いた話ですが、ある時、日本と各国の若者たちが揃って比叡山に登ったそうです。彼らは比叡山の霊気にうたれ、感動するのですが、インドネシアから来た若者が、「これはイスラムそのものですね」と言ったそうです。面白いですね。私はこれまでに数多くのイスラム国を訪問しましたが、この話を聞いて、非常に考えさせられました。インドネシアの若者が信仰しているそのイスラム教は、元来のイスラム教か、インドネシアのイスラム教か。インドネシアのイスラム教であれば、私は納得します。インドネシアのイスラム教は、インドネシアに元来あったアニミズムの影響を受けています。インドネシアのアニミズムは、この一帯の海洋国家に共通するものですが、その価値観は、比叡山の深い自然にこうべを垂れる、日本のアニミズムと通じるものがあります。つまり、比叡山に登ったインドネシアの若者が持つイスラムの価値観は、インドネシアが本来持っていたアニミズムの影響を受けた“インドネシアのイスラム”であり、比叡山に相通じる信仰心を感じて、「これはイスラムですね」と言わしめたとしたら、私は納得できるのです。
1960年代、ユネスコは、アブ・シンベル神殿救済のキャンペーンを行い、国際社会の協力を得たこの大事業は、大成功を収めました。続けて、モヘンジョダーロの修復、ボロブドゥールの修復と、文化財修復プロジェクトが進行していきますが、ボロブドゥールの修復をユネスコに依頼したのは、世界最大の信者数を誇るイスラム国家・インドネシア共和国、そして修復すべきボロブドゥールは、大乗仏教の文化財であり遺跡であるという事実。これは素晴らしいことだと思いませんか。ユネスコは、国際社会の協力のもと、10年間かけて、ボロブドゥールの修復作業を行いました。
ボロブドゥールの歴史を見てみると、8世紀に仏教国のシャイレンドラ王朝が着工します。完成は9世紀の前半。実はこの時、ジャワはヒンドゥー教国に戻っていました。ボロブドゥールを完成させたのは、ヒンドゥー教徒でした。そして、このチャンディー(寺院)を20世紀に復旧させたのは、イスラム教徒だったのです。私も、現地を3回訪れていますが、実際に現地で作業する方々の95%が、イスラム教徒です。その方たちが仏教寺院の修復作業に従事しているのです。私は参加していませんが、修復作業の起工式の当時の映像がNHKに残っています。その映像では、復旧工事を始める前に穴を掘り、牛の頭を埋めています。これは何を意味するかと伺うと、起工式に取り入れた儀式は、シャーマニズムの儀式であった、と言うことです。1983年の復旧完成式典には、私も立ち会いました。その時のユネスコ事務局長は、セネガル共和国のアマドゥ・マハタール・ムボウ氏。インドネシアのスハルト大統領も参加して、この2人がメインスピーカーです。ボロブドゥールを前に演壇を築くのですが、それはシャーマニズムの儀式が執り行われた場所であり、祭典の始まりには、イスラムのコーランが詠唱されました。私は、非常に感銘を受けました。宗教や信仰を超越して、聖なるものの復旧に対する喜びを表現しているのです。インドネシア全島から集まった舞踊団が次々に舞踊を披露するのですが、これらも宗教を超越しています。それぞれの島々の伝統に則った舞踊が披露され、全てが混然一体となった美しい絵巻を演出していました。こういった祭典の演出を可能にするのが、インドネシアのイスラム、と言っても良いのではないでしょうか。どう思われますか? ここで確認することができるのは、ハンチントンが主張する「文明の衝突」ではなく、「文明間の対話」です。
■海の道
このような文明の出会いが、なぜ起こったのでしょうか。ここに“海の道”の存在があります。拙著『文明は虹の大河』の中の「南海の大乗仏教の道」で、詳しく説明しています。これは、私が確信を基に書いた論文です。というのも、私の確信は、現地に行って、自分で歩き、自分で見てきた事実を基にしているからで、決して、本や資料からの情報や知識だけを頼っているわけではないからです。私の貫いてきた姿勢として、自分自身の目で見た上で確信した事象しか、文章に書きません。今までなぜ「南海の大乗仏教の道」が注目されなかったのかというと、それは蛸壺型の研究方法にあります。例えば、アンコールの専門家は、ボロブドゥールや中央ジャワの遺跡群に言及することが、ほとんどありません、その逆も、そうでした。私はこれに疑問を抱いていたのですが、そこにはアジアにおける植民地時代の影響もあったと思います。言い換えれば、植民地時代の宗主国の学者が書いた論文しか発表されない、という実状です。アンコールの場合は、フランス。ボロブドゥールであれば、オランダ。インドならば、英国。学問の世界にはこのような動きと縦割主義が、厳然と存在します。ボロブドゥールについては微に入り細に渡って書けたとしても、他のものは一切書けない、否、書かない、という縦割主義です。しかし、私の立場はユネスコという国際機関の職員ですから、学会のしがらみからは解放されています。各国の学者の方々とアカデミックな席で議論を重ねてきましたが、縦割主義を超越した見方を展開することが可能でした。この経験から、私が得た結論は「文明は生き物のように移動する」ということです。そして、これは私がよく引用する言葉ですが、フランスの哲学者ロジェ・ガロディの「文明は出会いによって子を孕む」というもの。このような文明の実相が、自らの現地調査と各界の方々との議論を経て、見えてきました。
北方仏教と南方仏教についても、ご説明しましょう。皆さんもご存知の通り、仏教には、ガンダーラの地からシルクロード、敦煌を経て、長安から朝鮮半島、そして、日本に伝播した北方仏教(大乗仏教)があります。これに対して、南の道は、セイロンからビルマ、タイ、あるいは、ベトナムまで伝播する道で、こちらを上座部仏教(Theravada Buddhism)、すなわち、南方仏教(Southern Buddhism)、とする説があります。ところが、この説だけでは、なぜ南海のジャワに大乗仏教の遺跡が出現したのかを、説明できません。南方仏教を全て、上座部仏教で括ってしまうと、ボロブドゥールの存在を説明することができないのです。
そこで、“海のシルクロード”という概念が浮上してきます。海のシルクロードによって、宗教も思想も動いたのだ、と。“海のシルクロード”という呼び方は、私がかつてユネスコの「シルクロード総合調査計画」に書き込んだことによって世界語になったのですが、それまで、“海のシルクロード”という名称は、受け入れてもらえませんでした。ヨーロッパでは「Spice Route=香辛料の道」、日本においては東京大学・三上次雄教授の名著に使われた「陶磁の道」が、通称とされていました。しかし、ユネスコの公文書に言葉が載ることは、大きな影響力があります。欧米でも、“海のシルクロード”という観念が一般的な名称となり、世界的な学会用語となりました。その後、ヨーロッパでは、『海のシルクロード』というタイトルの本が数十冊出版されるまでに至ります。陸のシルクロードだけではなく、海のシルクロードに着目すると、ボロブドゥールの意味が見えてきます。

ボロブドゥールの壁に刻まれている帆船のレリーフ
こちらの写真は、ボロブドゥールの壁に彫られた帆船の写真ですが、このような帆船の彫り物はボロブドゥールで3艘確認することができます。船の形に注目してください。こちらの船は、“アウトリガー方式”の船で、転覆を防ぐために、船の両側から外に、フロートが突き出しています。このような船はインドネシア独特のもので、中国のジャンク船にも、アラビアのダウ船にも、ありません。このように残っている船のレリーフの存在により、シャイレンドラ王朝も海洋交易を行っていたことが判ります。
海のシルクロードと大乗仏教の道
こちらは、私が作成した海のシルクロードと大乗仏教の道の図です。この赤いルートがローマとインドを結ぶ、紀元後1世紀から8世紀の、海のルートです。紀元後1世紀と言うと、ローマ帝国が隆盛の道を歩み始める頃ですが、ローマ帝国繁栄の一因に、東方地域との交易が挙げられ、そのインド洋交易を助けた要因が、 “ヒッパロスの風”と呼ばれる、貿易風の発見です。4世紀には衰退へと向かうローマ帝国ですが、1世紀は最盛期に向かう時代です。
インド洋の先には、インドがあります。着目すべきは、ガンダーラの位置です。赤いルートは、ガンダーラに行き着く、ガンジス川のルートなのです。ガンダーラは、ガンジス川上流に位置します。距離的には近くを流れるインダス川を使う方が、インド洋との往来は便利なはずです。NHK番組『仏教の道』ではインダス川が取り上げられていましたが、実は、インダス川は荒々しく、船が上流まで遡上することはとても難しいのです。一方、ガンジス川は穏やかな流れで遡上できます。昔の人の価値観は時間ではなく、そこに存在する“道”の重要性にあったのでしょう。アレクサンドリアで書かれた『エリュトラー海案内記』に、ガンジス川からバクトリア(今のアフガニスタン北部)まで道が通じている、という記述があり、インド洋交易による東西交流の影響が、ガンジス川を介して、ガンダーラにまで及んでいた可能性を、示唆しています。7世紀になると、ナーランダに仏教大学が誕生します。玄奘三蔵も訪れた場所ですが、ナーランダもガンジス川のルートにあります。
青いルートは、8~9世紀の大乗仏教伝播ルートです。このルート沿いにセイロン(スリランカ)が位置し、8世紀の国際的文化センターのひとつ、アヌダラプーラがセイロン北部に設立されました。アヌラダプーラは内地に建てられましたが、西側には、マンタイという海岸に面した港町がありました。残念なことに、マンタイという町は残っておりません。砂に埋もれてしまいました。海上ルートを辿った先に、長安があります。日本からの青いルートは、遣唐使の道です。さらに、青いラインが示すように、マレー半島を横断する、「陸を通る海の道」もありました。この陸の道に関しては、『文明間の対話』に詳しく書いていますが、川を利用した陸路の距離や効率、マラッカ海峡での海賊被害を考えれば、ここにあって然るべきでしょう。加えて、こちらの青いルートは、大乗仏教伝播の道だけにとどまりません。当然、「モノ」も流通し、経済活動も活発だったでしょう。海のルートの主役は、シャイレンドラ王朝のアウトリガー船であり、イスラムのダウ船だったのです。インド北部から始まる、陸上の青いルートは、北方仏教として伝播する「大乗仏教の道」です。それに対して、インド南部から始まり、セイロン、マレー半島を南下し、マラッカ海峡からボロブドゥールへと繋がる道、またはマラッカ海峡の海賊を避けて、スンダ海峡からボロブドゥールへと向かう道、さらに効率性を重視したマレー半島横断ルートが存在しています。これらの道は、北上し、広東から長安へ到達した後、大宰府、難波を玄関口に日本まで続きます。以上が、今のところ、私が辿り着いた結論ですが、この交易ルートを「モノ」と「文化」が、ダイナミックに往来していたことは、容易に想像されます。
■ボロブドゥールの発見と修復
ここで、ボロブドゥール発見と修復の歴史を見直しておきましょう。ボロブドゥール遺跡が発見されたのは、1814年です。イギリス人総督トーマス・ラッフルズが、“森に眠る寺院”の噂を聞きつけ、発見に至りますが、修復が最初に試みられたのは、だいぶ後になってからでした。1907年から3年間、オランダ人技師テオドール・ファン・エルプによって、復旧が試みられています。エルプが着手した際に見つかっていたのは、上部3層の円壇だけで、下部はすべて火山灰に埋もれていました。この時、方形壇の確認はされていますが、それ以上の作業は中断されています。その後、インドネシア政府の依頼により、ユネスコが正式に復旧作業に取り掛かったのが1955年、工事完成は1983年でした。1991年には世界遺産に登録されています。世界遺産条約が発効したのが1975年ですから、世界遺産登録はそれ以降になります。この復旧工事がなければ、世界遺産登録は難しかったと思います。
■ボロブドゥールの構造
さて、全容が明らかになったボロブドゥールの構造を見てみましょう。現地を訪れたことがある方もいらっしゃると思いますが、まずはこの“立体曼陀羅”をご覧ください。3段の円壇、その下部には6層の方形壇が配されています。一番下の基壇の一辺は111mで、頂上までの高さは31mあります。頂上の大塔に関しては、諸説ありますが、大塔の上に本来はさらに3層の傘が載っていたという説が、かなり有力です。私が注目しているのは、方形壇の壁に施された、全長3,500mの浮彫です。華厳経の世界を表す、素晴らしいものです。最初の部分は、本生譚(ほんしょうたん=ジャータカ物語)から始まり、釈迦の前世とその生涯を物語る石の書物になっています。全体で表しているのは、「多即一(たそくいつ)」という仏教の真諦(しんだい=絶対真理)です。これは禅に近いのですが、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ/Vairocana=大日如来)の教えですね。「一即多(いっそくた)」とも言いますが、壮大な宇宙観を表現したもので、「全体は部分に、部分は全体に“遍照”している」と意味しています。また、「Fractal」とは、部分が全体を表し、全体は部分に相似するといった構造です。ボロブドゥールにおいては、針状の小ストゥーパが“小さなボロブドゥール”を表現しています。つまり、「一即多」、「多即一」ですね。
立体曼荼羅を構成しているボロブドゥール
ボロブドゥールを上から見ると、曼荼羅の構造がよく判りますね。この円壇と方形壇の形に注目してください。これは“歩み寄り”を表しています。3段の円壇は、決して真円ではありません。どちらかというと、方形に近い。ただ、最上部の大塔を載せた円壇のみが、真円を描いています。つまり、円が方形に歩み寄り、方形が円に歩み寄っているのです。インドネシアの色々な場所に、ボロブドゥールの模型が展示されていますが、多くの模型は円壇を真円で表現されています。インドネシアの人たちも、間違えてしまうようです。ボロブドゥールの、この形が重要です。円形は天を、方形は大地を意味しています。したがって、ここでは天地が判然と別れているのではなく、天が大地に歩み寄り、大地が天に歩み寄っているのです。これこそが、ケドゥ盆地の風土にマッチした宇宙観と言えます。
ボロブドゥール寺院の断面図
次に、ボロブドゥール寺院の断面図をご覧ください。下方が基壇です。基壇にも、その上の方形壇にも、壁があります。時計回りで各壇を巡ると、右側に主壁、左側に欄楯(らんじゅん)が位置します。視界は遮られていますが、その壁には浮彫が施され、“石の書物”となっています。徐々に登り、円壇に着くと、パァーっと眺望が開けます。頂上となる大塔の上の部分は、3層の傘を再現しています。この傘の存在で、これがストゥーパなのだと判ります。傘がなければ、ストゥーパではないのです。
ボロブドゥールを真上から描いた構造図 胎蔵界曼荼羅図
続いて、こちらの写真は、ボロブドゥールの構造を真上から描いたものと、日本の胎蔵界曼荼羅図。この2枚を比較すると、ボロブドゥールが曼荼羅を描いているのが判ります。大塔が突出しているのも、この大塔の為にその他全てが造られているのではないか、つまり、ボロブドゥールはストゥーパではないかという説があります。これは、フランス極東学院教授パルマンチェの説ですが、私はこの説を支持することができません。
こちらの写真は、私が“向上門”と呼んでいる、ボロブドゥールの四面にある門です。門からは頂上へと向かう階段が続いています。
東側から入り、方形壇を時計回りに巡っていくと見える浮彫が、こちらの3枚です。
向上門の階段を上り、円壇に辿り着いた時の写真が、こちらです。
円壇ではこのように眺望が開け、そこには小さな釣鐘状のストゥーパがあり、その中には仏像が座しています。この写真のような仏像を、現在は見ることができません。なぜなら、仏像はストゥーパの中にあるもので、この写真は、ストゥーパが壊れ、剥き出しとなっている仏像を写したものだからです。この仏像は、長らく大日如来であるとされてきましたが、私の結論では、釈迦牟尼(しゃかむに)です。
この仏像が結んでいる“印”に注目してください。ダルマチャクラ、すなわち、釈迦の説法を表す転法輪印(てんぽうりんいん)ではありませんか。ダルマチャクラ・ム-ドラ(=転法輪印)には、2つの輪があり、2つの指が触れることで、「8」の字を描きます。「8」は、∞(無限大)であり、法輪が永遠に回ることを表し、仏陀釈迦牟尼(ぶっだ・しゃかむに)が結ぶ印です。20世紀後半までは、大日如来とする説が多かったのですが、現在は釈迦牟尼(しゃかむに)とされています。